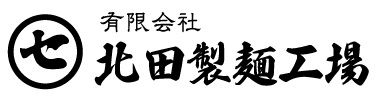業務終了(閉店)のお知らせ
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は明治27年(1894年)の創業以来129年に渡り、皆様の多大なるご支援のもと操業を続けてまいりましたが、諸般の事情により令和5年(2023年)9月30日をもって閉店・廃業となりました。
これまでに皆様から賜りましたご厚情に対し心より感謝申し上げるとともに、ご迷惑をおかけする結果となりましたことを深くお詫び申し上げる次第でございます。
皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
令和5年(2023年) 10月
有限会社 北田製麺工場
代表取締役 北田 壽美